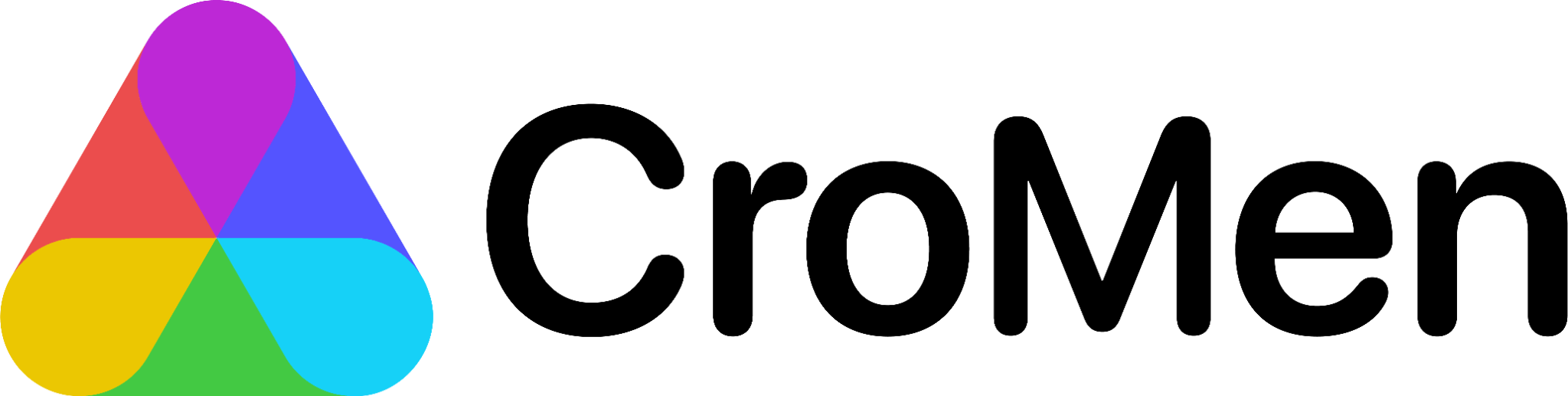「食事の制約があることで、諦めなければならない場面をたくさん見てきました。でも、本当は誰もが同じテーブルを囲んで『美味しいね』って笑い合えるはずなんです」。
東京農工大学の博士課程で流体力学を研究する傍ら、渡部裕也さんは、「食で困っている人をゼロにしたい」という大きなテーマに情熱を注いでいます。その純粋で力強い願いを原点に、誰もが自由に食を選び、共に楽しめる社会を目指す渡部さんの挑戦が、今始まろうとしています。
■Mission / Vision / Value
- Mission: 宗教やアレルギー、信条によって食事に制約を抱える人々が、もっと自由に食を選び、食べられる社会を実現する。
- Vision: 様々な制約に対応した食事を集めた自動販売機を設置し、誰もが食べたいものにすぐにアクセスできる環境を整える。
- Value:
- 幼少期を中国で過ごした経験や、大学時代の国際交流サークルでの副代表経験に基づく異文化理解力。
- 現在も食事に困っている人々との繋がりを持ち続け、彼らの声に耳を傾ける姿勢。
■自己紹介をお願いします
改めまして、渡部 裕也(わたなべ ひろや)です。東京農工大学の博士課程2年生です。研究分野は流体力学で、学部4年生の時から流体に非常に興味を持ち、研究を続けています。幼少期は中国の上海で過ごし、小学校の6年間をそこで過ごしました。その経験から、日本とは異なる文化圏での生活様式が自然と身についたのかもしれません。その後、中学時代は日本の千葉で過ごし、大学進学で東京へ。現在は、イギリスに半年間の研究留学中です。
性格的には、どちらかというと引っ込み思案な方です。自分から率先して何かをするということはあまりありませんでした。小学校の頃は先生に勧められて何かを始めたり、中学の部活動も先生や周りの友人たちに声をかけてもらって始めたりといった具合です。リーダーシップのスタイルについても、自分が憧れていたのは「やるぞ!」と皆を引っ張っていくようなタイプでしたが、自分はそうではないと思います。むしろ、皆がどう思っているのかを聞き、全員が納得できるような中間点を探していくタイプだと自己分析しています。
■なぜPDCに応募しようと思ったのですか?
「現状を変えたい」という強い思いが、PDCに応募した一番のきっかけです。 博士課程まで進み、大学には7年ほど在籍しているのですが、学部生の頃から感じていた「食に関する課題」が、何年も変わらずに存在し続けていることに気づいたんです。
これを何とかしたい、そのために自分に何が必要なのかを学びたいと考え、PDCに参加しました。
■PDCに参加して、自身にどんな変化や成長がありましたか?
PDCに参加して一番変わったのは、実際に行動に移すことのハードルが下がった点ですね。 以前は「こうしたらいいかな」「ああしたらいいかな」と考えるだけで止まってしまうことも多かったのですが、今はまず一歩踏み出してみて、その結果から得られたものを次のアイデアに活かす、というサイクルを少しずつですが回せるようになってきたと感じています。 まだまだ足りない部分も多いですが、この「行動力」はPDCの「内省」プロセスやメンタリングを通じて培われた成長だと思います。
■現在、どんな事業を考えていますか?
私が考えているのは、食事に制約のある方々、例えば宗教上の理由でハラル食が必要な方や、アレルギーをお持ちの方、あるいはビーガンやベジタリアンといった信念を持つ方々が、もっと気軽に、そして自由に食事を選べるようにするための事業です。
具体的には、そういった様々な制約に対応した食事を集めた自動販売機を、まずは大学のキャンパス内に設置することを目指しています。
商品は、保存期間が長いお菓子類やインスタント食品、飲み物、そして意外と入手が難しいハラル対応の調味料などを考えています。 また、近隣のハラル料理店やベジタリアンフレンドリーなレストランと提携し、お弁当を仕入れて提供することも検討しています。
本格的な自販機の設置はハードルが高いことも理解しているので、段階的なアプローチを考えています。まずは机に商品を並べてみて、どれくらいの需要があるのかを実際に確かめるところから始めたいと思っています。 その次のステップとして、大学内にある空いているロッカーを改良して、電子錠などを取り付けた簡易的な販売スペースとして活用できないかと構想しています。 こうして少しずつ実績を積み重ねていきたいです。
ターゲットは、まずハラル食を日常的に必要としている留学生です。彼らの多くは、毎朝自分で食事を準備したり、週末に作り置きをしたり、あるいは大学の生協で数少ない選択肢の中から我慢して選んだりといった状況に置かれています。 また、日本人学生の中にも、健康志向の高まりからビーガン弁当などに興味を持つ層がいることも分かってきたので、そういったニーズにも応えていきたいと考えています。
将来的には、他の大学にもこの取り組みを広げていきたいですし、さらには自販機同士がネットワークで繋がり、利用者同士のコミュニティが生まれたり、本来出会うはずのなかった人々が食を通じて繋がれるような、そんな仕組みも作れたら面白いなと考えています。
本記事は【前半】となります
後半の記事はこちら